第121号 2023/4/1発行
 假令身止 諸苦毒中 我行精進 忍終不悔
假令身止 諸苦毒中 我行精進 忍終不悔
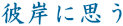 彼岸に思う
彼岸に思う
今年の桜は例年より早く開花し、現在境内の桜は満開です。
3月中旬に聞光寺境内の冬囲いの撤去をご門徒様にお願いしてやっていただきました。毎年お願いしていることなので段取りよく綺麗にそしてスムーズに片づけられてゆき春を迎えることができました。
昼と夜の時間が同じと言われ、天候も気温も落ち着いた時期が春・秋の彼岸といわれています。
このような場所で穏やかな気持ちでみんなと仲良く過ごすことができたら幸せだろうと、「彼岸」と名付けられたのではないだろうか。
3月21日のお中日には、お参りと法話だけでなく、今年は、コロナ前と同じように、お斎を出して賑やかに過ごしました。天気も良くマスクからも解放された感もあり、境内にあるお墓のほうは多くのご門徒さんが来られましたが、本堂ごほんぞんさまにおまいりすることをわすれないでください。
彼岸とは、生きている私は、亡き人(ご先祖様)たちから受け継いだ「いのち」を、浄土を感じられるこの時期に、仏様と真向かいになって、浄土に向かって歩み生きようとしているのかを見つめる時間として下さっているのではないだろうか。
私たちは幸福になろうと一生懸命に頑張っていますが、なかなか思い通りの幸福感を感じることのない生活をしているのではないでしょうか。
失敗した時に「あんなに一生懸命頑張ったのだから成功するのが当然なのに、出来ないのは不思議だ」と考えてしまいます。また反対に上手く成功すると「当然である。あんなに一生懸命にやったんだから」と思い、胸を張ったりします。
その行動をよく考えると、おかしく思いませんか。
私たちは、一生懸命頑張ったけれど、うまくゆかなかったときに勘違いを起こすことが多いのです。煩悩具足(心をわずらわし、身を悩ませる欲望が備わっていること)の私たち凡夫は、誰一人同じ人はいません。私たちは、何が起こるか分からない娑婆に住んでいるのですから、上手くゆくということは稀なことであり、あたりまえのことではないのです。
煩悩具足の凡夫が集まっての人間社会ですから、自分一人では成功することは難しいのではないですか。
小さな力の私は、知らないところで色々な物やたくさんの人に支えられ助けてくる不思議という働きを感じる感覚を育てることが必要ではないでしょうか。その働きを私たちに知らせて下さり、問いかけ呼びかけて下さるのが「仏様」というのでしょう。
仏になる教え
当院 井上宗温
今年の1月より大河ドラマ『どうする家康』が放送されています。乱世を終わらせた力強い印象のある徳川家康を、頼りないながらも周りの皆に支えられながら悩み苦しみながら進んでいく新しい家康像で表現されている物語となっています。
そんな「頼りない家康」であるのに対して、ナレーションでは最初から家康のことを「神の君」と表現しています。実際、徳川家康は亡くなられた後に東照大権現として、つまり神様として日光東照宮に祀られています。家康が日光に祀られる事となったのは家康の遺言かららしいですが、戦国時代を終わらせた家康は、死後もその後の平和を神様となって見守る事を望んでいたという事なのではないかと思います。
ところで、私たちは普段、神様になりたいと思っているでしょうか。なかなかそれを願える人はいないと思います。家康の様に大きな事を成し遂げることができたなら、神様にもなれるかもしれないが、自分にはそんな力はないし、畏れ多いことだと考えるのが常ではないでしょうか。
では仏様はどうでしょうか。私たちは仏様になりたいと思っているでしょうか。やはり、仏様になるなんて自分には畏れ多い事だと思ってはいないでしょうか。
そもそも仏教とは仏(お釈迦さま)が説いた教えであると同時に、仏になるための教えです。ですので、仏教徒であるならば、仏様になることを願っていなければおかしな話だという事になります。けれども、私が仏になるという事に頷けないでいる私に、聞法し続けて行く事が大事だと浄土真宗では教えられています。
お寺では定期的に聞法会が開かれておりますので、どうぞご参加ください。
県外在住のご門徒様へ
新型コロナ感染が流行しだす以前は、ご家族が亡くなられた時には連絡があり、時間の都合がつけば出かけて行っていました。
また、関東圏であれば、都合がつかなければ、本願寺の出先である「真宗会館」(東京都練馬区)にお願いし、故郷と同じような費用で葬儀を執行して頂いていました。
しかし、コロナ禍の中、親戚や友達もお別れできないでいましたが、これからは柏崎からも出かけて行けるので、いつでもご連絡ください。
もし聞光寺から出かけて行っても、かかる葬儀費用にプラス旅費往復と宿泊費になります。
聞光寺が行っても行かなくても法名(俗にいう戒名)はつけさせていただきますが、院号を付けられなければ法名料はいただきません。
県外在住のご門徒さんの法要、葬儀で出かけさせて頂く事でよりご縁を深いものにしてゆきたいものです。
