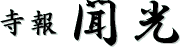第106号 2019/7/1発行
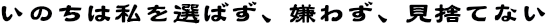 今、ここに生きている私
今、ここに生きている私
 携帯電話の時代
携帯電話の時代
最近小学生以上で携帯電話を持っている人は、どのくらいいるのでしょうか?携帯がなければ前へ進むことができないくらい携帯の需要が多くなっているようです。多くの需要に応えてゆける便利さは充分すぎるほどありますが、それと同等以上に問題を引き起こす原因にもなっています。
ちょっとした何気ない行動や事故が、人の人生を台無しにしたり、自分の人生を複雑なものにしてしまう人も多くなってきました。携帯は、社会生活をするにおいて、非常に助かるものではあるが、使い方や使っての生活が、自身をも壊してしまう事になることが多々あることを耳にします。医学関係者によると、1日5時間以上連続で毎日使っている人(特に子供)を病人として体面しないといけなくなっているとはっきりと言われています。
小さな、筋肉の発達してない子供が、携帯の小さなものを、近くで長時間神経を集中させると、目の筋肉が成長しなくなり、大人になる時に目に障害が出てくることになると言われています。子供たちは、一番近くにいる大人(両親・祖父母)を見て育ってゆきますので、親が時間のある時にいつでも携帯を使っていると、子供たちの生活でも、携帯を使っている事が習慣として生活になってしまうのです。使っていないと気持ちが落ち着かないような生活になってしまうのではないでしょうか。
子供たちには、携帯だけが便利で楽しく過ごせるものではなく、日常生活のあるとあらゆる事と過ごす事で、みんな関係して成り立っていることに、気づいてほしいと思います。目は目の仕事、耳は耳の仕事、肌で感じる気持ち等、私たち人間が、他の動物たちと違って独自に育ててきた感性を伝えてあげるのが私たち大人の仕事ではないでしょうか。
子供の時は、良い事も悪い事も区別なく、早く沢山の事を吸収します。人間が独自に進化をし、命を包み暖かく大きく育ててきたものまでも、失くしてしまうような現代社会の生活を、何とかしなければならないような気がします。大人がただ便利で楽しい都合のいい道具で過ごしている時間が、どんな時代社会を作ってゆくことになるのかを、少し立ち止まって考える必要があるのではないでしょうか。
私たちが生きるということは、色々な物や人と接してゆかなければならないので、自分の思い通りにはならないことのほうが多いのですが、接してゆかなければ生きてゆけないのが人間であり社会です。生まれたということは、誰でもが生きて行ける命を賜ったという事なのです。命を賜るということそのものが、共に仲良く協力しながら生きて欲しいという命そのものの願いを生きなければならないことになるのです。
成長期で知恵をつけなくてはならない時に、五感をたくさん使うことを放棄してしまったら寂しくつらい事ではないだろうか。私たちが今まで知らなかったことや、気づけなかったことが沢山あると思いますが、それを探すのは大変むづかしい事でしょう。それには沢山の人たちが、私と違った経験や体験が、私の経験や体験に大きな知恵を与えてくださるのではないでしょうか。そして、楽しく明るい道が示されるのではないだろうか。
機械は、便利で沢山のことを教えてくれるけれども、それに頼ってしまうと、柔らかさを失くしてしまい、大きくて自由な発想が出来なくなってしまうような気がします。
大人と子供、共に育つことは、一緒になって沢山の光を皆からいただくことではないでしょうか。
変更になりました
聞光寺報恩講の日程が変わり、10月25・26日の2日間となりました。
25日の午前中は、この1年の内に亡くなられた聞光寺檀家の方々の一周忌のお参りを、家族等の身近な方と聞光寺の本堂で、亡き人を偲ぶ法要を行おうと思います。話を聞き、一緒にお経をゆっくりと読み、お斎をいただくという会です。
午後は、報恩講(お引き上げ会)ということで、お話を聞き、近くのお寺様10人程の方々と、格式高い作法と読み方で、「正信偈」を朗々と読みます。
午前・午後両方の参詣をいただき、本堂が賑やかになってほしいと思っております。関係の方には、出欠のお手紙を8月頃にお出ししようと思っております。
聞光寺京都神木旅行
最近、団体として京都本山のお参りや、本山への納骨の機会を作ってきませんでしたが、この秋、10月8〜10日の2泊3日で計画いたしました。
賑やかにゆきたいと思いますので、沢山の方々のご参加をお待ちしております。
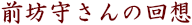 亡き人をしのぶ会
亡き人をしのぶ会
新橋 中村信男
平成30年、境内の桜が満開の頃でした。今年もきれいだねと膝をさするながら、しんみりと話を始める。
この頃で、終活について考えるようになった、ポックリがいいかジックリがいいか、日本人はジックリ逝く人が多いようだね。介護する、介護される事も念頭におくべきだと熱弁になる。前坊守さんがよく話したことに、寝たきりにはなりたくない、コロリと逝きたい。コロリ観音は、願いをかなえてくれるのか、信心次第だと手を合わせて笑う・・フフフ・・
人生の終わりまで自分らしく生きたいと、不自由な体で京都、東京によく出かけたもんだ。たまげるやら、あきれるやら心配でした。京都で転んで、やさしい女学生に助けられたが、オラ、ショウシかったと笑いながら話してくださった。今思うと暇乞いの旅だったんですね。
天気のいい日は、手押し車で境内を散歩したり、訪れる人たちと話したり、賑やかな幼稚園を見るのが日課になっていたようです。前坊守さんの話は続きますが、おしまいにします。
「宗祖親鸞聖人七五〇回御遠忌 讃迎第四回法話会」に参加して
真宗大谷派三条教区第十組機関誌『衆会』掲載
聞光寺門徒 上野昭一
平成も最後の4月10日午後1時30分、定刻通りに十組法話会は開催された
会場:柏崎市城東の行通寺本堂
講師:長岡市長福寺のご住職 北島栄誠師
講題:宗祖のおことばに学ぶ その二
講師先生は、本法話会四回シリーズの第三回目に引き続いてのご法話。手慣れた語り口、よく通る澄んだ声、改めての自己紹介をされた。生まれ育ったご自身の寺院が中越地震での大被害で苦難苦渋の選択の末、現寺院に入寺されたとのことを淡々と話された。
さて、宗祖のおことば、真宗聖典を中心に言葉で言い足りない処は文字で書いての説明
「浄土宗のひとは愚者になって往生す」
御遠忌法要にむけて、末燈鈔、浄土真宗の教え等々判り易く丁寧になされた。
当を得た、今回の法話会、有意義に聴聞させていただいた。