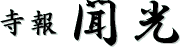第104号 2019/1/1発行
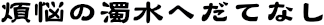 煩悩の濁水へだてなし
煩悩の濁水へだてなし
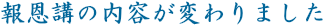 報恩講の内容が変わりました
報恩講の内容が変わりました
真宗寺院で最も大切に勤めている法要は、報恩講(お引上げ・お取り越し)です。
本山では十一月下旬に八日間厳修されております。それぞれ末寺で勤められる日や日数が違いますが、聞光寺におきましては十月の二十五日より三日間勤めております。
私の来るずっと以前(明治以前)は、六日間勤めていたようです。
少し遠い方は、私が来た頃でも、十五人ほどの方が二泊してをられました。
今は三日間勤めておりますが、遠い方でも日帰りになり、泊まられる方はおられなくなりました。
初日は、午前中に推進員の総会がありますので、午前は残ってお参りされる方が多少おられるのですが、お斎を食べられると、その方たちの多くも帰られます。
たくさんの方から来ていただければ、賑やかな報恩講になるのでしょうが、どうお誘いしたらよいのでしょうか。
そのような状況が、長い間続いておりますので、来年から報恩講を二日間のお勤めにしようと思っております。
初日の午前は、その年に亡くなられた方のご家族と共に、亡き人を偲びながらご一緒にお参りをし、お話を聞き、お斎をいただく集まりを考えております。
参加人数、お斎につかれる方の人数などは直接お手紙でお聞きします。
午後は毎年のように、お話しを聞き、近隣御寺院様とご一緒に大逮夜のお参りを勤め、「御伝鈔」を拝読いたします。
二日目は、午前九時より推進員総会をして、十時よりお話を聞き御満座のお勤めを近隣御寺院様とご一緒にお勤めいたします。
先代には申し訳ないけれど、二日間で頑張ってみようと思っております。今から時間をとって報恩講の日を空けておいてください。
毎年、賑々しく沢山の方とご一緒にお勤めをし、親鸞聖人のお心を訪ねて新しい一歩を歩んで行きたいものです。
真宗門徒の生活は、「報恩講に始まり報恩講で終わる」と言えるような法要にしたいと思っております。

十一月二十一〜二十八日まで行われる本山の報恩講。本山本堂が満堂になっています。来年、一緒に報恩講のお参りにゆきませんか。
 毎日が新しい日
毎日が新しい日
昨年の後半は、色々なことがあり半年が長く感じられました。
まだまだ元気に、お寺を取り仕切ってもらえると思っていたおばあちゃん(前坊守)が急に亡くなられて、裏方の仕事が想像以上に入ってきて、今でも混乱が続いています。
今までやっていなかった事を足しながらするということは、ぎこちなく手間と時間がかかるものですね
おばあちゃんは、八十歳を超しても、こんな面倒な会計のことまでキッチリとやっていたんだと、ただただ尊敬し、頭が下がるだけです。
そのような姿を見ていた私たちは、元気にやっているおばあちゃんから仕事を取ってはいけないと思いやっていただいておりました事が、よかったのか?わるかったのか?
少しづつでも引継ぎをしておけばよかったと思っています。
私たちの歩みは、毎日が新しい発見ということであり、一日として同じ日が無いという事です。
年を取れば特に自身が気付かないうちに変わっていることが多いようです。
お互いに気付き気付かれる存在で、一緒に生活することが大切であり、必要な事ではないでしょうか。
お内仏のお掃除・仏具磨きをしよう
最近、たくさんの人が集まる法要の様子がちょっと違って見えるのです。
よく見ると、私の知らない人が多くいるように思えるのです。
住職になって二十五年を過ぎたのですから、それぞれの家でも、世帯主が変わられたお宅も多くなったからでしょうね。
そして今の時代は、親子それぞれの世帯が、核家族として生活していることが多くなっているようですから、仏教の作法がよく伝えられていないように思われます。
お内仏(お仏壇)では、お花を時々変え、きれいにしてお参りはするけれど、お掃除や仏具磨きは、長い間されておられないように思います。
掃除をすると仏具の位置が分からなくなるのでできませんと言われます。
新しい年を快よく迎えられるように、お磨き・お掃除をしませんか。
仏具の名称と、置く場所をかいたお内仏の絵をお届けいたしました。
お参りをするときの焼香の作法が宗派によって違いますので自分の宗派(聞光寺は真宗大谷派です)の作法をされれば何処ででも大丈夫です。
真宗大谷派は、二回焼香することとしています。一連の焼香の作法は別紙に書いてお届けいたしました。