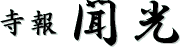第103号 2018/10/1発行
 無明の闇を破する
無明の闇を破する
 突然はびっくり、間違うものです
突然はびっくり、間違うものです
死は誰にも突然やってきます。
「がん」と告知されて言われた日がくるまで生きておられるとは限りません。
突然は、私のところへも、大切な人嫌な人関係なくやってくるのです。
頭では分かっているのに、その時はなかなか受け取れない行動をとってしまいます。葬儀に向かっては緊張が続いたり、色々なことを短時間で考えなくてはならないので、間違うことが多く起こります。
そんな中でケガをしないよう注意することが大切です。私は玄関で足を踏み外してしまいました。
ほとんどの人は、いつか来るであろうと予測はしていたけれども、その時まで緻密に考えてはいないでしょうから、びっくりして時間が止まったようになるのではないでしょうか。
しかし、その時から一気に同じ方向を向いて、あっちからも、こっちからもくるのです。思っていたことが、落ち着いてくる度に抜け落ちていたことに気が付きます。
私たちは、娑婆で生きる煩悩具足の人間なのですからその事をしっかり受け止めて進んでゆくしかないのです。
「私はよくわかりません」と言われるほうが素直で「しっかりとできます」と言えるのは、たくさんの死に出会っているか、仕事上関りが多い方たちです。
「慣れていますから、次は大丈夫です」と言える時の「次は」自分の時か、連れ合いの時なので、冷静にできないと思います。
葬儀関係の時は、間違うことが多々あると思い、あいさつの初めに、「急な事で落ち着いた気持にはなかなかなれないので、色々と間違うところがあると思いますがお許し下さい。」と、簡単に頭礼をしてから、本来の挨拶をするのはいかがでしょうか。
 聞光寺のおばあちゃん
聞光寺のおばあちゃん
聞光寺にきて私は37年を過ぎました。
先日亡くなられたおばあちゃん(前坊守)は、66年を聞光寺で生活したことになります。
66年の中で一番がっかりしたことは、平成19年7月16日の「中越沖地震」で崩壊した本堂の再建会議の時に「私のお葬式は聞光寺の本堂から出してほしい」と言ったことが再建する勢いになったようです。
私は養子に来たので、聞光寺・井上・柏崎等はほとんど解らないけれど、同じ環境を過ごしてきたおばあちゃんから事あるごとにおそわったり聞いたりして、聞光寺の皆様のことをわかるようになってきました。
新しく家族になった者は何もわからないので、色々なことを知ってもらいたい、後をしっかり継いでほしいという気持ちで、食事やお茶の時などに、聞光寺、井上の歴史やそれに連なる沢山のご縁を教えていただきました。
おかげで早いうちに、先代住職以上に聞光寺や、ご門徒さたちとの関係を知ることができました。
しかし、八百年の歴史の深い部分を、もう少し聞いておけばよかったと残念に思っています。
またおばあちゃんは、八十歳を過ぎても、ずっと元気で最後まで幼稚園のことやお寺の行事の段取りを先頭に立ってやってきました。
その頑張りや性格・記憶力の良さは、葬儀に来られた七十年来の友達(県立高田北城高校の同級生)は、一同に声をそろえて「あの人は死ぬまで北城高校の生徒会長だったね」と、言っておられました。
そのように人をまとめたり、仲間として優しく関わったりすることによって、寺という必要だけれども中々行きにくい所を、特に檀家が多く歴史のある聞光寺という寺を、誰でもが入って来れるように、浄土真宗の敷居の高さはもともと低いものであることを、私たちに気付かせて下さった方ではないでしょうか。
複雑な現代を生きてゆく私たちに、本当に必要な場所としての、誰でも来やすい所を作ってし下さったのではないでしょうか。
聞光寺を現代に必要な場所として育ててゆく歩みを忘れないで、前へ進んでゆくたいと思っております。
おばあちゃんありがとうございました。


聞光寺二十四代坊守 井上五百子さんの思い出のまま
法名 林正院釋尼聞香さん。こんにちは。時は忙しく過ぎてゆきます。
「ひざの調子はどうだね」と健康を気遣う言葉が飛び交うたわいもない話に笑顔があふれ、多くを語らなくても言葉に重みがある。
人の悩みや、思い出は千差万別だと、相手の立場に立って、先ず話を聞き、何ができるかと共に考える。
やさしい声で諭すような語り口で戒めたり、勇気づけたり、なつかしい語らいが、今も胸にこだましている。
いつも冷静で威張らず、気どらず淡々として優しいところが好きだった。
話の続きはお浄土でと、8月14日早朝に旅立った。・・・
思いはつきません。
本当に長い間お世話になりました。
心よりお悔やみ申し上げます。合掌
(市内新橋 中村 信男)