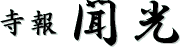第76号 2012/1/1発行
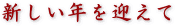 新しい年を迎えて
新しい年を迎えて
新年あけましておめでとうございます。
新しい年を迎えるにあたり、前の年を振り返ってみなければならないでしょう。
昨年は、私たち浄土真宗の宗祖である親鸞聖人の七百五十回御遠忌の年でありました。
聞光寺におきましては、二班に分かれて70人ほどの方々と参詣し、沢山の方々と出会ってきました。4・5月は、全国からの団体参拝の人たちで京都中が賑やかでした。
しかし、御遠忌の始まる少し前に、東日本大震災があり、その地震によっての大津波による被災者は数えられないようです。
死者・行方不明者は約二万人で、いまだに行方不明者が約三千五百人もおられます。
また、台風や大雨によっての山崩れ等による土砂災害、それに伴う川の氾濫等で、多くの被災者を生みました。
自然災害とは言いながら、それらを受けて生きてゆかなければならないのが私たちの生活です。私の手には負えない、思いどおりにはならないのが自然です。
災害が起きて人間の力の無さに気付かされ、何とか対処するのだけれども、それもまた壊されてゆく事の繰り返しをしているようです。
力の無さ、無知さを知らされ反省はするけれど、すぐに忘れてしまう生き物が人間なのでしょうか。その愚かさを無くすために精進するのではなく、愚かさをしっかりと受け止め、自然と共に生きるための生活をすることに努めなければならないのでしょう。
常の生活が、「おかげさま」と感じられる柔軟な温かい心を育てなければならないのではないでしょうか。
愚禿と名告られた宗祖の七百五十回御遠忌に出合えたことは、私たち人間にとって、よりはっきりと、今まで人間の都合がより良くなるように築きあげてきた文明が、生き物の根源である命を少しずつ削り取っていることに気づかされる出会いだったような気がします。
宗祖親鸞聖人は、越後へ来られて初めて人間に出合われておられます。
『一念多年文意』の中で宗祖は、「凡夫というは、無明煩悩われらがみにみちみちて、欲もおおく、いかり、はらだち、そねみ、ねたむこころおおく、ひまなくして臨終の一念にいたるまでとどまらず、きえず、たえず」と表されておられます。
そんな私でも、こうして生きておられるのは、私を生かそうとしている仏様のお働きによるものではないでしょうか。その働きに「有り難う。おかげさまで」としか言えない私があるのです。
ご縁は無量に出会うもので、良い悪いを選べないのです。出会ったご縁はすべて受け取ってゆかなければなりません。
私の都合ではなく、自然のおすそ分けを頂く生活が、私たちには一番快適な生き方ではないでしょうか。
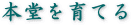 本堂を育てる
本堂を育てる
震災で倒壊した本堂は、七月には再建します。少しずつ姿を現してゆくのを見ていると、嬉しくなってきます。
しかし、本堂は建物ができたから完成ではありません。
お寺にはたくさんの行事があります。それらの行事は、寺の人間ばかりではなく、檀家の方々やご縁のある方々が集まり、育ててゆくところです。
浄土真宗の本堂は、参詣の間が広く造られているのは、迷い悩み苦しむ私たちを、救いたいという仏様の願いを覚られたお釈迦様のお心や、そのお心を生活として歩まれた先輩たちの生きようやお心と、私の生きようを照らし合わせ、本当の自分に会わせていただく場なのです。より多くの人たちが集まられるようになっているのです。
娑婆の真っただ中で一生懸命に生きてゆく事は、意に合う事合わない事、良い事悪い事もたくさん起きてきます。
そして、迷い悩み苦しみながら、いろいろな人たちとの間柄(ご縁)を生きてゆかなければならないのです。そんな私たちだからこそ、仏様と出会う生活が必要なのです。
各ご家庭にもお仏壇がありますが、お寺の本堂は、日常気付かない、感じない事などを、私たちに示して下さる御講師をお願いして、違う人が共に生きている事を学び、違うままでも一緒に居れる世界を生きる方向として有る事を確認してゆく場所としてあるのです。
そんな本堂を造ってゆくためには、僧侶だけではできないのです。檀家の方々やご縁の深い方々と共にでなければならないのです。
是非、お寺へお出かけ下さりお育てください。
重厚な屋根
釋 定信
今日12月14日は素晴らしい晴天となった。
建築中の本堂の大屋根の瓦が朝日に輝いていた。
本堂最上部の大棟の鬼瓦は、聞光寺の紋入りで大棟両端に陣取って、重厚で風格のある形と大きさは見事なものだ。
大棟には、聞光寺の山号である「無量山」が記されている。
大棟・降棟・隅棟の大屋根の様式が、東本願寺の御影堂と同じだ。
朝日を浴びながら瓦葺き職人が、手際よく隅棟の鬼瓦を二人がかりで取り付けていた。
瓦葺きをはじめ屋根周り工事が、降雪前に終わればいいのに気がもめた。
屋根破風の錺金具の取付は年内にできないようなので寂しいが待ち遠しい。
一年を振り返り
聞光寺当院 釋 宗温
一昨年の4月に柏崎に戻ってきて昨年は二年目ということでしたが、私は昨年より本山の嘱託補導を始めました。
嘱託補導というのは、本山に来られる奉仕団の方々を日程中案内する仕事です。
奉仕団は清掃奉仕をして本山を綺麗にしようというのが目的ですが、同時に二泊三日あるいは一泊二日の本山での生活を通して、真宗門徒としての生活を確かめる場でもあります。
その案内役という事で、私自身改めて一から確認することができました。
例えば、「お内仏」について。
「お内仏」というよりも「お仏壇」と呼ぶ方が多くおられますが、真宗では「お仏壇」ではなく「お内仏」と呼ぶのが正しいのです。
「お仏壇」というのは、ただの箱、入れ物であって、その中の御本尊こそが大切なのだから「お内仏」と真宗門徒は呼ぶのです。
そして「お内仏」が表しているのは浄土です。
だから、「お内仏」の中にある仏具一つ一つにもきちんと意味があるのです。
ろうそくの灯りは、如来の知恵の光を表し、香炉の香や線香は、その如来の働きが隅々までゆきわたることを表します。また、花瓶の花は、その美しさと同時に、命あるものは必ず朽ちてゆくのだということを気付かせてくれる。
だから、花瓶の花は造花ではなく、きちんと生花を供え、日々お給仕をしてゆかなかればならないのです。
普段何気なく目にしていたけれども、本山で改めて「お内仏」の中に、真宗の教えが表されているのだということを学び、きちんと皆様に伝えてゆかなければと考えさせられた一年でした。