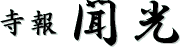第74号 2011/7/1発行
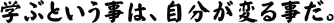 学ぶという事は、自分が変る事だ。
学ぶという事は、自分が変る事だ。
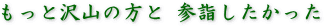 もっと沢山の方と 参詣したかった
もっと沢山の方と 参詣したかった
今年は「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌法要」の年であり、七高僧の一人であり宗祖の先生である法然上人の八百回忌の年でもあります。
東西本願寺をはじめとする浄土真宗各派と浄土宗各派での法要が、京都を中心に厳修されるという事なので、春から関西地域は相当賑やかになるのではないかと、法要参拝の団体を引率するにあたって心配しておりました。
ところが、3月11日に大地震(後に東日本大震災と名付けられる。)が起き、地震はもちろんだが、それによる津波、そして、東電福島第一原子力発電所での事故と爆発、それによる放射能汚染と風評被害等によって、たくさんの方々が多大な被害を受けられました。また、死亡者(15508人)、行方不明者(7207人)がおられる状況なので、被害地の復興はままならないようです。
真宗大谷派(東本願寺)では、3月の第一次御遠忌法要は中止になり、荘厳を平常にして、「被害者を悼む会」として厳修されましたが、聞光寺は第二次の4月21日のお逮夜に参詣をしましたので御遠忌法要として厳修されました。
お逮夜のお参りは、午後1時半からなので、柏崎を午前5時半に出発しました。早い時間は、バスの中も静かでしたが、京都に近づく頃には賑やかになっていました。
運転手さんとガイドさんのお陰で、予定より早く着く事ができ、お参りの前に、綺麗に修復された御影堂をバックに記念写真を撮りました。
参詣席は全部指定席だったので、自分の席を確認してから各々が境内にある記念品売り場へ行かれた様です。
本願寺門首の挨拶の後、五十年に一度の御遠忌なので、厳粛な法要は僧俗共にのもと、お正信偈と念仏のうねりが、御影堂いつぱいに広がって素晴らしく感動いたしました。
終了後、来年から修復に取り掛かる阿弥陀堂の素屋根と、そこから見る御影堂の素晴らしさに驚きながら宿へと向かいました。
22日は何時降るかわからない天候の中、京都観光をしました。
昼前に納骨の方々は分かれ、祖廟でのお参りをしました。
帰る頃から雨が降り出し、亡き人が別れを惜しんでいるかのように感じられました。
午後からは雨の中ではあったけれど、この時期に居るはずの外国の観光客と修学旅行生がほとんどいないのでゆっくりと観光ができました。
震源地から遠く離れているのに、大震災の影響が非常なものだと感じました。
23日は朝から雨、まずはじめに聞光寺本堂の佛具をお願いしている若林仏具店で、本堂で使われる仏具や、修復される仏具、そして、御本尊様が安置され、本堂の中心に置かれる白木で造られた須弥檀を見学しました。
須弥檀に漆が塗られ金具が付けられた姿を想像した時熱いものが込み上げてきました。
本尊様の前で誰もが落ち着けるお寺にして行かなければならないと、あらためて思いました。
その後、京都市立美術館で親鸞展を見学して、名残惜しいけれど京都をあとにし、柏崎へとバスは走りました。
御遠忌法要参拝と納骨
釋 定心
平成23年4月21日(木) 晴、宗祖親鸞上人七百五十回御遠忌法要参拝と、最愛の妻、法名慧光院釋尼妙踊を、大谷祖廟に納骨する為に、檀家の皆様と大型バス2台に分乗して、午前5時半に聞光寺を立ち京都に向かった。
朝が早いせいか車内は静かで、ベテランバスガイドが名調子で、通過地の説明が小気味よい。京都までの6時間が楽しく、やがてバスは、御影堂門前につく。
全国からの参拝の人で境内は賑やかだが、宗務役員に案内されて堂内の団体参拝席に着く。先ず御真影にお参りをする。
法要開始までのしばしの間、堂内を見ると、全ての物が修復されていた。特に内陣御厨子が美しく神々しい。
午後1時になると逮夜法要が、真宗宗歌から始まる。挨拶。感話・法話と講師の言葉には熱気があって、時の経つのを忘れる感動を覚えた。
正信偈真四句目下を、大勢の僧侶と参拝者が一体となって唱える声が天に届けと広い堂内に響き渡る。最後は、恩徳讃を唱和して法要が終わった。
聞光寺一行は、阿弥陀堂素屋根内の見学だ。二階三階で ご修復の歩み展を見て、先人のご苦労を偲び、三階から見る御影堂の瓦が大きいのに驚き、屋根破風の錺金具が光り輝いていた。
京の宿、緑風荘に着く。早速く風呂でゆっくりと手足を伸ばして
「じょんのびじょんのび」。
お楽しみの宴会は、舞妓宴会だ。京都の味覚とホテル自慢の美酒佳肴に出会ってゆったりと酔いしれ、芸達者な舞妓さんの踊りで気分が一層盛り上がり、心地よく沈没しました。
4月22日(金)どんよりとして雨が近いようだ。金閣寺・龍安寺の見学が終わると、納骨組は一行と別れて、住職の案内で大谷祖廟へ向かう。今にも降りそうな空模様になってきた。事務所で納骨の手続きが終ると降り出す。
祖廟本堂で最後のお経をあげ、親鸞聖人御廟に納骨する事が出来た。
亡妻の笑顔が脳裏に浮かんで、思い出が走馬灯のように巡る。私の人生で最大の幸運は妻と出会った事で、何事も妻と相談して二人三脚でやってきたが振り返ると感謝だけだった。
三十三間堂と二条城の見学は、観光客が少なくゆっくり出来た。
今日の宿は駅前のホテルだ。チェックインが済むと駅前の散策に出かける。観光客が少なく、駅前がちょっと寂しい様だった。
夕食はバイキングで飲み放題と嬉しいね。飲んで食べて楽しいおしゃべりが遅くまで続いた。
4月23日(土)小雨 若林仏具店で聞光寺関係の佛具を見る。
製作中の宮殿は大きく立派だ。見事な彫刻を施した重層的構造の、目が肱む様な美しい中に、御本尊様を奉安申し上げるわげで、完成が待ち通しい。
京都市立美術館で親鸞展を見学し、平安神宮を参拝して観光全日程は終った。
日常の雑多なことなどすっかり忘れて、和気あいあいの雰囲気で、楽しい上山参拝と納骨旅行が無事終った。
無情に降り続く雨の中、名残つきない京都をあとに帰路に着く。
「宗祖親鸞聖人七百五十回御遠忌」に参詣して
前坊守 井上 五百子
聞光寺団参の第二陣は、4月27日から29日までの二泊三日で、第十組のお寺方10名と聞光寺関係17名の計27名で行ってきました。
28日は結願日中(御満座)のハイライトである板東曲(ばんどうぶし)が勤まるので、是非その盛儀をお参りしたかったのです。
板東曲という声明の由来は、一説には、鎌倉から南北朝時代、本願寺第三代覚如上人の頃に、関東の同行による勤行が始まりとも伝えられています。
念仏と和讃を繰り返し、体を力強く前後左右に動かして拍子をとりながら勤めるもので、大変ダイナミックな声明であり、今では大谷派のみに伝えられているものです。
朝9時から3時間にわたって繰り広げられた声明の素晴らしかった事、お参り出来て幸せでした。
七百回御遠忌の時、さて次の七百五十回御遠忌にはお参り出来るかなあと思ったのですが、生きながらえて、孫に手を引っぱってもらいながらお参り出来た事は有難い事でした。
大勢の皆さんにお世話おかけしまして有難うございました。
なむあみだぶつ 合掌