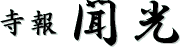第72号 2011/1/1発行
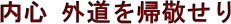 内心 外道を帰敬せり
内心 外道を帰敬せり
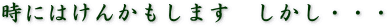 時にはけんかもします しかし…
時にはけんかもします しかし…
昨年、朝鮮半島に於いて戦争が起りそうな気配となった事が、幾度かあったようです。
しかし、今は何とか衝突しないでいるようですが、何時戦争になっても不思議でないような状況になっているように感じられます。
よく考えれば、韓国と北朝鮮の境になっている北緯38度線は、国境ではなく、休戦ラインなのですから、二国の間では戦争は終わっていない事になります。
同じ民族なのですから、早く仲よくして一緒になってほしいものですが、今たっている場所と、行こうとする方向があまりにも違いすぎるのでしょうか、統一はまだまだ先のように思われます。
ほんの150年前の日本では、大きな枠組みはあったけれど、それぞれの国(藩)が他の国を拒み監視をしたり、独自の言葉や習慣を造りだして、小さな島の中で沢山の国が権力争いをしていたのではないでしょうか。そして、江戸末期から明治初期に於いては、日本という一つの国を造る為に、同じ民族どうしが殺し合いをし、沢山の命の上に統一されたのが今の日本なのですから、意見を同じようにして同じような方向を向くようになるという事は大変難しい事なのですね。
時代が変わったと言っても、「平和ボケ」していると言われるくらいの日本が、もっとも近い外国であり、いまだに休戦状態にある朝鮮半島の二つの国の平和の為に、力を尽さなければならにのは必然でしょう。
しかし、70年程前には、その半島を侵略し、我が国として治めた事が、今でもそこの人達の心に、深い傷として残っている事は伺えます。
前述の事を認めない日本人も多くおられますが、史実として心に深く刻み、その心で日本の国造りをして行かなければ、一番近い外国とも「共に生きる道」が開かれてくる事はないのではないでしょうか。
平和が続きすぎて、わずか70年前にしてしまった煩悩具足としての人間の行為を忘れてしまったのでしょうか。
日本が今こうしてある根っこには、一番古い親友として、また先輩として日本の伝統文化の基礎を教えてくださった歴史があるのです。ゆえに、どんな事があっても「共に生きよう」とする努力が必要なのではないでしょうか。
ちょっとばかり賢くなったり、裕福になってもいばる必要はないのです。喧嘩もするでしょう。良い時もあり、悪い時もあるのだから、お互いに兄弟のように助け合わなくてはならないのです。
何故なんでしょう?
最近何処の寺院からも聞こえてくる言葉があります。
それは、「お参りする人が少ない。」という言葉です。
聞光寺におきましても、一番重きを置く11月の報恩講(お引き上げ)は、2日間で延べ50人程度です。一番多く来られる盆内(今年は7月9日・10日・16日・17日)は、私が聞光寺へ入った頃は、千人を超えていましたが、昨年(平成22年)は、4日間で356人(お斎を食べた方)の方しか来られませんでした。毎年少なくなってきているように感じられます。
本堂がなく、毎年日が変わるせいでしょうか?誰もが自由にゆっくりしたい土・日曜日のせいでしょうか?本堂が出来れば以前(7月11日〜14日)に戻るのですが・・・
その他の「仏教講座」「人生講座」等で素晴らしい先生をお呼びしても、参加者が少なく、先生に申し訳ないような時が多々あるのです。
私達は、興味がひかれるか、楽しければそこに集まります。ならば、今のお寺は興味がひかれないし、楽しい場所ではないと言う事ですね。
昔はお寺へ老若男女多勢の人達が、聴聞に集まって来られていました。
やっている事は、昔と今であまり変わっていないようですが。足をはこばせる何かがあったのでしょう。
これからは、古くからの伝統行事は、大切にしなければならないけれども、今の時代を生きている人達が気を止める何かをも発信しなければならないのでしょうね。
内からでは見えない事が外からだと見えてくる事が沢山あると思います。内は内で一生懸命頑張りますが、外から感じた事を教えて下さい。
行事や催しを、内と外とで作りだす事で、お互いが楽しみながら育ってゆく事が、お寺に願われているのでしょうね。
ご連絡
聞光寺におきましては、当院が帰ってきまして1年近くなります。仕事も大分慣れてきたようです。昨年のご回檀は、一緒に回りましたので、多くの方々と出会う事が出来たことと思います。今年方のご回檀は、私と手分けをしながらお伺いするつもりでおります。二人で回りますので、いつもの年より早く伺わせて頂く事になると思いますが、ご了承ください。
尚、伺わせて頂く2日くらい前に、地域の世話人さんにご連絡を致します。
宜しくお願い致します。
 一寸一言
一寸一言
最近、葬儀・法事等の後で催されるお斎の時に気になった事があります。
お斎は、亡き人を偲び亡き人とご縁の深い方々と共に、これからもっともっとご縁を、より良く深いものにして行く為の懇親会ではないでしょうか。しかし、お斎が、普通の昼食会と変わらなくなっている事が多くなってきているように感じられます。何故かと言いますと、ほとんどの人が、自分の席から動かずに食事をしている景色が多いからです。
お斎の開催者である施主(喪主)夫妻は一生懸命に、ご挨拶やお礼をして、ご縁を大切にしておられるのですから、その兄弟姉妹や子供達は、食事会に呼ばれているお客さんになっているのではなく、施主と共に、亡き人と、この家の為にわざわざ来て下さった本家や分家・親戚の方々に、お礼、あるいは今後の実家と自らのご縁を深めて行く出会いの場所、時間にして行かなければならないのではないでしょうか。
如来大悲の恩徳は
身を粉にしても報ずべし
師主知識の恩徳も
骨をくだきても謝すべき