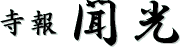第61号 2008/4/01発行
 浄土を本国として今を生きる
浄土を本国として今を生きる
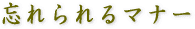 忘れられるマナー
忘れられるマナー
私たちの連絡手段として最近は、携帯電話が多く使われています。用のある連絡が、直接自分の所にかかって来るのですから大変便利です。何時でも何処でも何処へでもかけられる。自分にとっても相手にとっても無駄のない動きができるようです。
ある人は、「何処にいても連絡が取れるのでゆっくりとお茶も飲んでいられない。鵜飼いの鵜みたいなものだ」と言い、またある人は、「これが鳴るまでは、俺の自由時間だから仕事さえやっていれば楽でいい」と言う人もいます。

「携帯電話」とは、身に付け持ち歩く事の出来る電話の事で、持っている本人に直接連絡する為であるならば、その人だけに分かればいいことなのではないでしょうか。
ならば、携帯電話の着信音は必要ないのではないですか。
しかし、現実は色々な所から色々な音の着信を耳にします。それらの音は、私にとっては必要のない雑音として聞こえてきます。
必要な人に振動等で、他の人に分からないような方法で知らせる事で用は足りるのではないでしょうか。私だけ着信に気付けばいいのだと思います。
新しい技術が生まれたら、今までなかったその技術を使うにあたってびマナーを伝えなければならないと思います。携帯電話においても、ふぞくするマナーがあると思います。
新しく生まれてくるマナーはあまりないと思いますが、新しく生まれてきた技術の便利さが、もともとあるマナー(例えば、お茶会では金属類や硬いものを外して席に入る)を見えなくしているようです。
映画館、音楽鑑賞会、観劇等の会場内は、落ち着いて静かにしなければならない所です。当然入る前には携帯電話の電源を切らなくてはならないはずです。
しかし、館内放送で、電源を切ることや、マナーモードにするように注意が流れています。館内にいながら、信用されなくなった寂しさを感じてなりません。
どんな時でも、仕事から離れる事が出来なくなった時代には、必要な道具かもしれないけれど、仕事が最優先される生き方が、私の生まれてきた意義と言えるのだろうか。
前記のような事が沢山あるのではないでしょうか。デート中、食事中等は、携帯を気にしないでゆっくりと本音で出会う時間になれば、家族や友達と、もっともっと楽しく有意義な時を過ごせるのではないでしょうか。
携帯電話を切るということは、もしもの為に、自分の居場所をはっきりさせておく事が必要となります。また、切るということは、信用を伴う行動が要求されるという事ですね。
他の人に迷惑と感じられるような着信の電話は、携帯電話とは言わないと思います。
私に連絡が必要な人が、私の所に発信した連絡を、私がすぐに受け取る為に、身に付けたり近くに置く事によって、すぐに対応することの出来る電話を「携帯電話」と言うのであって、最初から着信音はいらないのではないだろうか。新しいものを使うには、大きな自己責任があると思います。
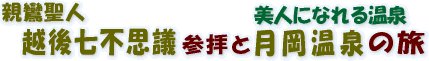 親鸞聖人越後七不思議参拝と美人になれる温泉月岡温泉の旅
親鸞聖人越後七不思議参拝と美人になれる温泉月岡温泉の旅
ゆっくりした旅です。
檀家の方ではなくてもお誘いしてご参加下さい。
賑やかに回りましょう。
| 期 日 | 平成20年6月4日(水)〜5日(木)1泊2日 |
|---|---|
| 旅 費 | 28,000円 |
| 人 員 | 40名様 |
| 申込金 | 5,000円 |
| 〆 切 | 5月10日 |
| 1日目 | 聞光寺(8:30)→柏崎IC→巻潟IC→味方笹川邸・曽我平沢記念館 →山田・焼鮒(田代家)→新潟・ふるさと村 《昼食》→ →鳥屋野・逆竹(西方寺)→礎町・木揚場協会→月岡温泉(16:30) |
|---|---|
| 2日目 | 旅館(9:00)→京ヶ浜・八房の梅・数珠掛桜(梅護寺)→ 安田・三度栗(孝順寺)→三川・将軍杉→阿賀の里《昼食》→ 沢海・北方文化博物館→田上・つなぎ榧(了玄寺)→燕三条IC→ 柏崎IC→聞光寺 |
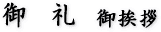 御礼御挨拶
御礼御挨拶
林 星児
柔らかな陽射しの中、境内でもふきのとうたちが大きく伸びをして春を喜んでいます。私にとっては四度目の春ですが、一身上の都合により、この3月末日を以て聞光寺様を辞することと致しました。

僅か三年、至らぬところばかりでしたが、多くの檀中の皆様からお育てを賜り、私にとっては本当に実り多く幸せな時間でした。
会う度に「お聞光寺の若ぇの!」「林さん頑張ってっか!」とお声をかけて戴いた事。時には立場や世代を超え、人間同士として話をさせて頂いた、そのような思い出の数々が胸に去来致します。
皆様から頂戴したご恩と教えを心に刻み、また新たな一歩を踏み出す所存です。古より会うは別れの始めとて覚悟してはいながら、いざ辞さんとする今、やはり心残りも多くございます。
新しい生活への希望は勿論ありますが、今は先ず皆様とお別れせねばならぬことに痛惜の念を得ません。
皆様どうか御身大切に、いつかきっとまたお目にかかる日があることを願いつつ、御礼と御挨拶に代えさせていただきます。
ありがとうございました。

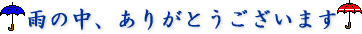 雨の中、ありがとうございます
雨の中、ありがとうございます

春を感じてきたお彼岸の前に、ご門徒の方数人にお願いして、冬囲いを外していただきました。
いつもながら本堂前の囲いもあって、10人ほどの人手が必要なのですが、雨が降っていたのに、少ない人数で一日で終わってしまいました。仕事をされた方は、「いつもより簡単すぎて張り合いがない」などと言われていました。
年2回の仏具磨きは、あまりにも少ないので、数人で済みそうです。ご門徒さんが、お寺の中で色々発見できる機会なのですが、残念ながら今は・・・・
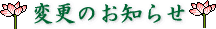 変更のお知らせ
変更のお知らせ
7月11日から14日まで行っていた盆内会は、本堂が倒壊いたしましたので、ご不便をおかけしますが、勤行・法話は仮本堂と庫裡を使い、おときは、幼稚園の遊戯室を借りて、12・13日(土・日)、19・20日(土・日)と二日ずつ分けて行う事になりました。
就きましては、人数の事がありますので、それぞれの都合によって変更があると思いますが
原則は、以前の11日の方は12日に、12日の方は13日、13日の方はあ19日、14日の方は20日に参詣をお願いいたします。
10月の報恩講は、25・26日(土・日)と年度予定に書きましたが、御講師先生の都合で26・27日(日・月)と変更になりました。
狭い仮本堂での厳修ですが、一生懸命勤めます。目の前に、ご本尊様と、御絵伝が拝見できます。
沢山の方々の参詣を楽しみにしております。
《編集後記》
7月16日の震災から8ヶ月が過ぎましたが、自身の生活はスマートさや張り合いが感じにくいのです。災害の後遺症なのでしょうか。皆さんはいかがですか?
中々後遺症は治らないでしょうが、しっかりと足元や周りを見て、前に進むことを考えなくてはならないのでしょう。
市の文化財になっている梵鐘は、庭に座っておりますが、去年発刊された本に載っているのと大分違うので、見学に来られた方は戸惑われる事でしょうね。